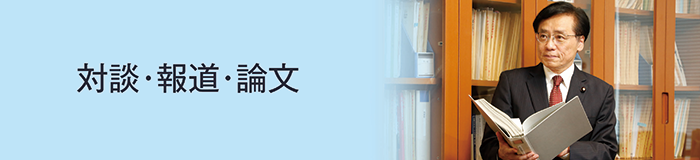能登半島地震一年 能登の被害実態に即した支援を国の責任で
参議院議員・能登半島地震対策本部事務局長 井上哲士
はじめに
「黙とう」──二〇二四年一月一日の能登半島大地震から一年となる今年の元日。羽咋市の「共同支援センター」で開かれた「追悼と再生への夕べ」に参加し、地震が発生した十六時十分に亡くなられた皆さんを悼み、被災者に寄り添った復旧・復興に力を尽くすことを誓いました。
日本共産党は発災直後に全国会議員が参加して「能登半島地震対策本部」(田村智子本部長)を立ち上げ、私は事務局長となりました。佐藤正幸石川県議や市・町議とも連絡を取り合いながら各議員がそれぞれの分野ごとに現地視察に行き、本会議や委員会での質問は団全体で百回近くになります。本部全体や議員ごとに政府レクや要請も重ねてきました。
日本共産党として二月に労組・民主団体の皆さんと一緒に「能登半島地震被災者共同支援センター(共同支援センター)」を発足させました。全国からたくさんの支援物資を届けていただいています。十二月末までで支援物資が三百五十㌧、五㌔㌘のダンボールで七万箱です。ボランティアはのべ八千人、義援金約三億円、地震が二億七千八百万円で、水害がプラス二千万円です。送ってくださるだけでなく、ボランティアとして自分たちで野菜も含めて支援物資を運んできて、それをいろいろな仮設住宅や自宅避難の方に持っていってもらっています。被災者の皆さんには大変喜んでいただいています。地震の直後は、お米と水と温かい食べものがほしいということでしたが、今は生活物資全般です。地震に豪雨が重なり、着るもの、食器・鍋、布団から座布団まで一切がダメになって、近所の店も潰れ、救援物資も頻繁に届かないのです。
訪問した際にお聞きした生の声や、医療・介護などの各分野の取り組み、課題などは共同支援センターに集約されています。県議や市・町議などを通じて自治体にも届け、私たち議員団にも届けられ政府要請や質問で生かしています。国会と現地を結びつけるという点でも、共同支援センターが大きな役割を果たしています。
被災者が「見捨てられた気持ち」と──まさに人災
私も地震の直後に輪島市に行き、それから何度も現地に行きましたが、ほぼ一年たつという今も驚くほど復旧復興が進んでいません。これまでいろいろな震災の現地を見てきましたが、遅れは突出しています。復旧復興がやっと進みだしたところに九月の豪雨災害でした。その直後も輪島市に行って、避難所や浸水した仮設住宅、輪島塗の仮設工房などで話を聞きましたが、「地震で自宅が被害を受け避難所に入り、金沢に二次避難して八カ月してやっと仮設が建って帰ってきたら、一カ月もしないうちにこの豪雨で浸水し、ふり出しに戻った」、「心が折れる。見捨てられているような思いだ」と、皆さん口々に言われました。
そのなかで災害関連死が地震の直接死を超えて石川県内で二百七十人(十二月二十七日現在)になっています。人口減少が深刻で、奥能登四市町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町)で四千百五十六人(七・五%)減り、四十代以下は千五百五十五人(九・四%)減った(十一月一日現在、同年一月比)との発表です。私は昨年の臨時国会の際、十二月九日の補正予算審議の本会議でこうした能登の実態を示して石破茂首相をただしました。首相がその前の所信表明演説への質問の答弁で、「災害を防ぐことはできないが、その後に起きることはすべて人災」と、かつての後藤田正晴・元内閣官房長官の言葉をひいたことを示し、地震の復旧の遅れが豪雨被害をひどくし、住民が暮らし続けるという希望を持てなくして、どんどん人口流出を起こしている今の状況は、まさに人災ではないかと迫りました。
地震災害の復旧がほとんど進んでいないもとで、これだけの豪雨災害が重なったのは前代未聞です。さらに、過疎と高齢化が進む半島という能登特有の困難があります。これにふさわしい支援を行うことが必要です。
求められる地震と水害一体の対策
地震で多くの建物や道路に深刻な被害が出ました。一方、地震と豪雨は、被害のあり様が違います。地震で被害を受け、住むためには修理をしなければいけないが、なかのものはなんとか持ち出せるケースもあります。豪雨災害のひどさは、たとえ家が壊れていなくても、土砂と流木で家のなかが泥だらけで、取り出して使えるものは一切ないことです。
農地は、土砂で荒地のようになってしまっています。川は堤防が壊れて直せない状況です。地震で農地や水路、ため池などの農業用施設や機械などに大きな被害が出ました。その復旧途上の収穫期である九月の豪雨で約四百㌶の農地に土砂、流木が堆積しました。農水省は、そのうち百七十㌶を今春の作付けに間に合わせたいとしていますが、それ以外の見通しは示されていません。
たとえば罹災証明は地震と豪雨災害を一体のものとして出すということになっていますが、すべての施策をこうした未曽有の複合災害にふさわしく、一体のものとして避難所・被災者に届ける必要があります。能登に住み続けることができる希望を与える対策を示してこそ「政治は決してみなさんを見捨てません」ということが伝わります。その責任を果たしていないことが人災を起こしているのです。
能登半島の特徴に合わせた支援を
能登半島は、第一次産業が基盤の地域です。高齢化と過疎化が進み、一番の働き手が減り、高齢者だけの住まいが増えています。自治体の広域合併とリストラが進められ自治体の職員も減っているもとで、復旧復興の担い手自身が厳しい状態にありました。さらに能登の地形上の特徴もあります。交通の便が悪く、土地が少ないため、復旧に当たる人が行くのにも大変で時間もかかるし、平地が少なく泊まる場所を確保できない。初動は、非常に困難があったと思いますが、それでも一年たってこれだけの遅れとなっていることは、被災者への支援やそれを担う体制の面でもふさわしい対策を国がとってこなかったという点で、人災と言わなければなりません。
自ら被災しながら必死で頑張ってきた自治体職員の皆さんも、膨らんだ救援実務、行政実務に追われ、さらに豪雨が来たことによって心が折れたような事態になっているのです。巨大な被災に対応する現場の行政能力を超えているのですから、三月の段階で中断している職員の全国的な応援派遣で新たな対策をうつなど、国が責任を果たすべきです。
被災者の生活と生業の再建こそ中心において
阪神淡路大震災の際、国と自治体は「創造的復興」の名で、被災者を置き去りにして神戸空港建設など大型プロジェクトを進め、住民本位の復興が妨げられました。この「創造的復興」は東日本大震災にも引き継がれました。日本共産党は石川県の馳浩知事が早々と「創造的復興」を打ち出した時から、「被災者を置き去りにして開発や交流人口頼みの街づくりにならないか」とただしてきました。
一方、こうしたやり方ではなく、人々の生活となりわいの復興こそ中心にするべきだという流れが広がってきました。阪神淡路大震災の時には住宅再建への補助制度は全くありませんでした。震災後、市民の運動が大きく広がり、被災者生活再建支援法がつくられ、住宅再建への補助制度ができました。中小企業支援も融資しかなく補助制度はありませんでした。これも運動が広がり、東日本大震災のときには、被災した企業へのグループ補助金というものができました。
能登地震について財務省は、四月の財政制度等審議会で「将来の需要減少や維持管理コストも念頭に置き、住民の意向を踏まえ十分な検討が必要だ」、「被災地の多くが人口減少局面にある」としています。要するに、そのような人が減るところに金をかけたくないと露骨に言っています。
今、インフラやなりわい、医療や介護の復興が進んでいないのに、一方的に「自立」を強いて支援を縮小する動きが強まっています。しかし、能登の特質を考えたときに、これまで以上に人間を中心とした、そこに住んでいる人が主人公の復興をやらなかったら、もう人口流出は止まらない。「人間の復興」と表現する研究者もいますが、そのことが大きく問われています。
住まいの再建
■狭すぎる仮設と地域バラバラな避難
まずは住まいの確保と住宅の再建です。
仮設住宅に入居できた被災者から、さまざまな不満の声が上がっています。一番多いのは狭すぎるということです。仮設の多くは、小さなキッチン・台所と四畳半に一人ないし二人です。高齢者の方も多いので、例えば介護用ベッドが必要な人がいるわけです。しかし、それを入れたらもういっぱいで他には置けない。お風呂の段差が高すぎるなど、高齢者が多く住んでいるという特性などを考えずに、とにかく数あればいいということになっています。北陸の人たちは、子どもたちも呼んで集まるような広くて、収納機能もたくさんある家に住んでいたから耐えられない。「自分たちの暮らしてきた住宅とはまったく違う」、「ストレスが溜まってしかたがない」との声がよせられています。
八割ぐらいが鉄板プレハブ型なので、断熱が効かず、暖房や冷房の効果も悪い、洗濯干し場がないとかさまざまな要望があります。
阪神淡路大震災のときに地域のコミュニティとは関係ない仮設をつくってしまい、孤独死が増えたこともあり、その後、新潟・中越地震や東日本大震災で集落コミュニティを大事にした仮設をつくる努力がはじまりましたが、過去のそういう教訓が全然生かされていない。大規模な仮設住宅をつくっても集会場をつくらなかったところもあり、住民が集まる場所もない。こうした要望に応えた改善が必要です。
これらの教訓をふまえ、今後の災害復興住宅建設計画で住み続けられる展望を示すことが求められます。
■罹災証明の改善と早期発行への支援
住宅の再建へ半壊以上の被害を受けた建物の公費解体がすすめられていますが、完了したのは申請の三九%にとどまっています(十二月二十二日現在)。
公費解体や住宅再建の支援を受けるには罹災証明が必要ですが、それも大きなネックになっています。専門でない自治体職員がおこなっている家の被害判定に対する不服が多く、奥能登四市町でおよそ三割が再調査をしています。十月に金沢で日弁連が、「能登半島地震 二人三脚の復興を目指す~罹災証明問題を考える」というシンポジウムをおこないましたが、そのなかでも専門家ではない自治体職員がやることの限界や実態とあまりにもかけ離れた判定になっていることが指摘されていました。
しかも、この再調査の結果が出るまで時間がかかる。判定の結果で支援されるお金が違うわけですから、再建できるかどうかの見通しも持てない。こうして全体が遅れています。松村祥史防災担当大臣(当時)も現場で不服を聞いているということで、見直しをしなくてはいけないと言っていますが、早急に改善が必要です。
この問題も本会議で取り上げ、住宅としての機能が失われていることに着目をした被災判定にするよう求めました。実際には、傾いていて中にいるだけで気分が悪くなることなどがあるにもかかわらず、外から見てあまり壊れていないからと、実態に合わない判定がされているというような判定のあり方自身も変えることが必要です。さらに専門性をもった職員を派遣する支援を求めました。
■被災者生活支援法の改正を
本会議では、被災者生活再建支援法の改正も求めました。
今、支援金の限度額は三百万円です。そもそも法改正をしたときから比べても、二〇二四年の春の時点で、資材自身が一・五倍になり、さらに工賃もあがるなど、物価全体が高騰しています。国は建設費の高騰を理由に特例で災害公営住宅建設の補助の限度額は引き上げることを検討していますが、そうであれば住宅再建でも、能登の六市町にだけ特例交付金二百万円をプラスするだけでなく、どの被災地でも六百万円に引き上げ、実態に合わせて一部半壊も対象に広げるなど法改正をすべきです。そうしないと、住まいの再建の展望が見えず能登に戻れない被災者が多数生まれます。
医療、福祉、介護、教育──暮らし再建に不可欠
■全額国の負担で医療・介護費用免除の継続を
暮らしの再建のためにも医療や福祉、介護へのいっそうの支援が必要です。本会議でも強く求めました。被災者は医療や介護の窓口負担は国の財政支援により免除になっています。もともと二〇二四年九月末の期限が年末まで延長されたのですが、九月末のギリギリまで決まらず、避難者や病院関係者もどうなるのかと心配されました。「新しい年を少なくとも不安を解消して迎えようと思ったら早く延長を決めるべきだ」と求めたところ、厚労省は十二月十三日に免除措置への財政支援の半年間の延長を決めました。被災者の願いにこたえるものです。しかし、これまで全額補助でしたが、最大二割の自治体負担が求められる場合もあることは問題です。
また、被災地にある特養老人ホームが被災した場合、そこの被災者は金沢などの福祉避難所に避難していて、この場合も負担は免除になっています。少しずつ元いた施設が復旧してきていますが、実際にはそこの職員も被災していて、人手が足りないため、元通りには受け入れできないのです。にもかかわらず、それは地震が直接の原因ではなく、避難者が帰れるのに帰っていないのだからと、食費を請求するなどの事態が起きています。こうした実態とかけ離れた機械的なやり方で追い出しをかけることを国と県が一体になってやっています。中止を求めました。
輪島市では九つの小学校を子どもの減少と予算不足で三つにする案が出ています。学校がなくなれば集落が衰退する悪循環を招きます。昨年の衆院選で初当選した堀川あきこ議員が、復興・災害対策特別委員会での初質問(十二月二十三日)で、「共同支援センター」が行ったアンケートの内容を紹介し、子どもの就学支援や心のケア支援の拡充を求めました。
■自治体まかせにせず、思い切った支援を
福祉施設の職員のみなさんも子育て中の人が多く、その人たちが金沢市に避難し子どもも市内の学校に行っているから戻れない。結局、人員が確保できず、その施設に入っていた人は戻れないという悪循環で、どんどん人口減少に拍車がかかっています。
厳しい条件の下でも医療関係者の懸命の努力が続けられています。壊れたままのところでも診療を一生懸命やっておられます。しかし、奥能登四市町では、二十八あった民間医療機関のうち七割以上が休診や診療時間を短縮するなど地震前の体制に戻っておらず、廃業も一件あったと報道されています。これらも自治体任せでは解決できないので思い切った支援が必要です。
この間、全国でも進められているように、能登の珠洲、輪島、七尾の各市と穴水町に四つある公立病院を、人口が減って赤字が続いているから統合しようという計画があります。震災という事態になっても、その計画が止まっていません。大変広い地域で、総合病院だけど地域医療の基幹病院的役割を果たしているようなところが、一つになってしまったら、通院も困難になり、住み続けられない。これも人口減に拍車をかけることになります。こうした統合計画はやめ、地域医療をしっかり確保することが必要です。
さらに体調などを理由に在宅避難を選ぶ高齢者や障害者の実態把握や支援の遅れも問題です。本会議で、国として、地方自治体の取り組みへの支援の強化とともに、災害救助法の対象にこうした福祉支援を加え、国が費用を負担するようにするべきだと求めたところ、首相からは「災害救助法で想定される救助活動に福祉の観点を盛り込み、これを国庫負担の対象とすることを検討いたしております」と答弁がありました。ぜひ実現したいと思います。
道路と水道などインフラの復興と豪雪対策
地震で大きな被害を受けた上下水道の復旧には全国からたくさんの水道職員の皆さんが現地に入り進めてきました。寸断されていた道路も、応急復旧が進んできました。しかし、地震で山が緩んでいたもとで九月の豪雨により山肌の崩壊などが起き、道路の寸断とともに、水道管の破損も発生しました。一刻も早い復旧が必要です。
これから雪の季節に入っていきます。北陸の雪は水分が多く重いのが特徴です。今は山が崩れたり、堤防が壊れたところも土嚢を置いてあるだけで、根本的な工事をやっていません。いつそれが再崩落するかわからない。それで道がストップになったら、また孤立集落になります。普段でも雪解けの頃に雪崩がおこりますが、今回は特に危ない。豪雪期までに道路やインフラの復旧、土砂への対応などできる限りやらなくてはいけない。この問題への対応について、臨時国会の田村智子委員長の代表質問への答弁で石破首相は、除雪機械の増強や小型の除雪機の貸し出しなどを政府の経済対策に盛り込んだと言っていましたが、人的体制も含めた大きな支援が必要です。
従来の枠超えた支援で生業の再建を
地震で海底が隆起して半島の外回りの漁港が全滅しました。輪島市の港も隆起しましたが、一部だけは船が出入りできるという状況です。今、輪島港だけが少し掘り下げて、漁港として復活できるように進められています。それ以外は対策のめどが立たたない状況です。昨年一―九月の能登六市町の主要港漁獲量は、前年の五六%の九千八百八十三㌧となっています。
農業は地産地消が中心でしたが、お米や野菜がおいしいし、水産物と共に能登牛もあり観光客を惹きつけてきました。一次産業の農業、漁業などが能登の経済の重要な柱でしたが、隆起と山崩れや豪雨による土砂で、それらが壊滅的な打撃を受けました。
ここをどう立て直していくか。第一次産業はもう手の打ちようがないという国の今のやり方では能登は復興できません。半島という地理的困難な状況はあるけれども、だからこそ培われてきた伝統や文化、産業があります。能登の農業や漁業は、金沢市も含めての石川県の観光の魅力です。合わせて、輪島塗や珠洲焼などの伝統産業・文化、今度日本酒がユネスコ無形文化遺産に登録されましたが、おいしい日本酒もあります。それがトータルで石川県の魅力です。石川県の経済全体から能登を切り離して金沢市などの観光振興ということではなく、ほとんどが地震被害で休業中の和倉温泉などの復旧支援を含め、第一次産業、観光、全部一体のものとして再建するということでやらないと、能登にも石川県にも未来が見えてこないと思います。
輪島塗は今回、仮設工房の建設を国の制度でやれるようになったのですが、東日本大震災ではじまったグループ補助金以前に、二〇〇七年の大きな能登地震が最初あったときも、伝統産業である輪島塗に対し基金を使った補助制度をつくった経緯もあります。今回、県としての基金もつくられたわけで、そういうものを活用し、なりわいの再建に対して思い切った従来の枠にとらわれない支援をすることが必要です。
志賀原発は廃炉に
原発ゼロの必要性も改めて浮き彫りになりました。志賀原発では地震でさまざまなトラブルがありました。北陸電力はすぐに安全宣言をしましたが、七月になって、壊れた変圧器が復旧するのに二年ぐらいかかると発表しました。事実を隠して、安全だ安全だと言って、実は重大なことが起きている。原発を運転する電力会社としての資格が問われています。そもそも北陸電力が再稼働の申請で言っていた断層が連動する想定は九十六㌔㍍でしたが、それが今回は百五十㌔㍍も連動しました。それ自身がもう想定とは違います。政府の地震調査委員会は昨年八月二日、近畿から北陸にかけての沿岸や沖合でマグニチュード7以上の地震を引き起こす恐れがある活断層が二十五カ所に上るとする調査結果を発表しました。そのうち三カ所は今回初めて活断層と評価されたものです。地震列島日本で安全な原発などありません。
私も発災直後に志賀原発のすぐ横を通って輪島市に入りましたが、震度七を記録した志賀町では道路が寸断され、多くの建物が倒壊していました。およそ避難などできない。避難計画がまったく絵に描いた餅だと実感しました。
いったん事が起きれば大変なことになることがこれだけ明らかになっているのに、政府が十二月十七日に公表した国の中長期のエネルギー政策の方向性を示す「第7次エネルギー基本計画」の原案は全く逆行する内容です。
原発については、東京電力福島第一原発事故以降、政府自身が掲げてきた「可能な限り原発依存度を低減する」という文言を削り、再生可能エネルギーと合わせ「最大限活用」を打ち出しました。事故の教訓を投げ捨て、原発回帰をいっそう鮮明にした形です。さらに原発の新規建設について踏み込み、岸田文雄政権が二〇二二年十二月に決めた「GX(グリーントランスフォーメーション)基本方針」では廃炉を決めた敷地内と限定していたのを、電力会社が同じなら敷地外でも可能にし、新規建設をしやすくする方針としました。新規の原発についても「開発・設置に取り組む」としました。到底、受け入れられるものではなく、このような計画を許さない運動の強化が必要です。
避難所の抜本改善と備蓄の強化
九〇年代から日本は「大地動乱の時代」に入っていると言われます。確かに能登も二〇〇七年以降、連続して大きな地震が起きていて、十一月二十六日にもM6・6の地震がありましたが、元日の地震とは違う断層が動いたものです。二〇〇〇年代初めに出された危険度マップでも、能登も熊本も鳥取なども全部ノーマークで、熊本ではわからなかった地層が動いて大地震となりました。どこで大きな地震が起きても不思議ではないのに、石川県の場合はそれをまったく反映しない地域防災計画が一九九七年から更新されていません。今回の震源に一番近い地震の被害としては、死者七人、避難者二千七百八十一人という想定になっていました。
ですから避難所に指定されている学校にもわずかしか備蓄品はなく、しかも地震は正月だったために帰省した皆さんで人口が増えていて、あっという間になくなってしまいました。その後、一定の改善はありましたが、九月豪雨被害があって再び避難所を開設した際には、元の劣悪な状態に戻っていました。あれだけ地震被害があったのだからしばらくはないだろうと思っていたのでしょうか、備蓄品が改善されていなかったのです。
避難計画をきちんと見直すことと、それにふさわしい備蓄品を現場でも確保することは能登の教訓からも大事です。さらに、今回のような県全体におよぶ被災の場合にも対応できるように、国としての必要な分散備蓄をおこなうことが必要です。
■新たな備蓄支援とスフィア基準に対応した避難所新指針を能登でも全国でも
私は昨年三月の予算委員会で、各国の赤十字社などをメンバーとする団体が策定し、避難所の満たすべき基準として国際的に使われてきたスフィア基準を生かすために、イタリアなどの例を参考に避難所・避難生活学会が提唱している、トイレ、キッチン、ベッドを四十八時間以内に避難所に届ける「TKB48」を示し、備蓄強化を求めました。石破首相が昨年十月の所信表明演説で、このスフィア基準を、「発災後早急に、すべての避難所で満たすことができるよう」にするとのべたので、必要な備蓄をどう強化するのか本会議で質問しました。
それに対し首相は、〇補正予算で、キッチンカー、トイレカーなどを整備する自治体の取り組みを支援するための新地方創生交付金の予算を計上した、〇災害時に利用可能なそれら備品を平時からデータベースに登録しておき、発災時の対応に活用する、〇国による全国各地への迅速かつ確実な物資のプッシュ型支援を可能とするため現在の立川防災合同庁舎に加えて新たに全国七カ所に分散備蓄をする──の三点について答弁がありました。
さらに内閣府は十二月十三日に避難所運営に関する自治体向け指針を改定しました。これまでは「参考にすべき基準」にとどまってたスフィア基準に対応するよう新規準では求めています。
トイレに関しては発生当初は「50人に1基」、その後は「20人に1基」を配備し、男性用と女性用の比率を一対三とするよう推奨。自治体には簡易トイレの備蓄や誰もが使いやすく清潔なトイレの確保に努めるよう求めています。
入浴施設は「50人に一つ」との基準を示しました。避難所内の一人当たりの居住スペースは、畳二畳分に相当する「最低3・5平方メートル」を明示。段ボールベッドなどが置ける広さの確保と雑魚寝解消をめざし、簡易ベッドと間仕切りは「開設時からの設置」を促しています。
このほか、被災者に温かい食事を提供する必要性も強調しており、地域内でキッチンカーを手配するなどの取り組み事例を紹介しています。
避難所の改善と備蓄の強化は多くの人々が求めてきたことで、日本共産党も要求してきたものです。とりわけ過去の経験が生かされていなかった能登の避難所の劣悪さを見て、改善を求める大きな声が上がり政府を動かしました。
ぜひ全国の地方自治体で、新しい国の支援を活用した備蓄の抜本的強化や新指針に基づく避難所の改善を強く求めてほしいと思います。もちろん、この基準を今の能登の避難所にきちんと適用させることが必要です。
一人ひとりの要求を運動を通じて実現し、さらに政治を前へ
被害状況は、災害によっても、地域によっても違います。被害状況を制度に当てはめるのではなく、解決のために、制度をどう柔軟に当てはめるか、足りなければもっと増やせと求める姿勢こそ必要です。能登は保守的な地域で、住民の皆さんは「我慢強い」と言われています。仮設などを訪問しても、最初は「こんなに支援してもらって」と言われてますが、よく対話するとさまざまな不満や願いが出されることも多いのです。一人ひとりの要求を大きな声と運動にして国や市町に迫り、実現させていく流れをもっと強めることが必要です。
総選挙後の国会は、自公過半数割れの下で、予算案も法案も与党だけでの強行はできなくなりました。これまで、被災者生活再建支援法の改正などを、野党が求めても政府は拒んできましたが、こうした願いを実現させる新しい条件が生まれています。これを生かし、能登の被災地の願いの実現に力を尽くしながら、さらに国民の命と暮らしこそ最優先する新しい政治へと前に進めるため、比例代表候補として夏の都議選・参院選挙での躍進を勝ち取る決意です。(いのうえ・さとし)